
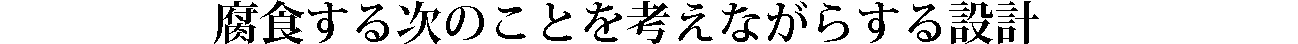 コストパフォーマンスが高く、
コストパフォーマンスが高く、
金属を守る表面処理
金属の世界での「腐食」を「錆び」と言い、これを「防食」する手段の一つが「鍍金:メッキ」です。塗装やメッキなどでバリヤー(障壁・膜)で金属面を完全に遮蔽できれば良いのですが、 完全な膜を作ることは難しいので、また作った膜が更に腐食する次のことを考えながら設計することが大切になります。
黒染め(四三酸化鉄被膜)
-
黒染め処理は主に鉄系の素材に処理されます。鉄鋼の表面に酸化皮膜を形成する処理となります。被膜が1μ程度と非常に薄い為、寸法精度が必要となる製品に向いています。また、価格が安いことも特徴としてあげられます。色は光沢のある黒色です。目的としては防錆がメインとなります。
無電解ニッケルメッキ
-
メッキ液の中に含まれる成分が酸化し、放出された電子によって金属ニッケル皮膜を生成するメッキ方法です。通電を必要としない為、樹脂等の絶縁体にも処理することができます。無電解ニッケルメッキは膜厚を均一につけることが出来る為、高い精度が求められる製品・複雑な形状の製品によく利用されています。
ニッケルメッキ
-
ニッケルは適度な硬度、柔軟性がある強磁性の金属です。ニッケルメッキの種類は多く、光沢、半光沢、無光沢、つや消し(サテン)、黒ニッケル、二・三層メッキなどが実用化されています。工業的用途として、スズ、銀、金メッキの下地メッキとしても幅広く使用されていて、メッキ工業の中で、もっとも重要なメッキのひとつです。表面が特別に反射防止特性を必要とするときは電気黒色ニッケルめっき、または無電解黒色ニッケルめっきが使用されます。
亜鉛めっき
-
亜鉛めっきは、電気を流すことで皮膜が生成され、この電気的性質から電気の流れやすいところや、製品の端部分が膜厚が厚くなる傾向があります。逆にくぼんだ箇所や電気的に陰になるような場所は、めっきが薄くなる傾向があります。
めっき後にネジが入りにくくなるとか、精度の求められる箇所のクリアランスが、悪くなるとかいうトラブルも、膜厚や分布が原因することも有ります。
亜鉛皮膜は、亜鉛自体が腐食することで、素材の鉄の錆び(赤錆)の発生を防止する働きが有ります。亜鉛皮膜が錆びると、俗に「白錆び」が生じます。この白錆びを防止するために、亜鉛めっきの上からクロメート処理がされます。
ユニクロメッキ(光沢クロメート処理)
-
色は青みがかった銀色で、装飾用として選定されることも多いです。皮膜が片肉約10μと厚く膜厚の管理が難しい為、高い精度が要求されるような製品には向いておりません。また、他のクロメート処理と比較すると耐食性は劣るので、耐食性を重視するような場合にもおすすめしません。しかし、他のメッキ加工と比べ、低価格での処理が可能な為、量産品等には適している表面処理です。
クロメート(有色クロメート)、クロムメッキ
-
薄黄色で、最も一般的に処理されており、耐食性も良好です。3価クロメート。
黒色クロメート
-
耐食性が良好で装飾部品にも処理されています。耐食型 3価クロメート。
硬質クロムメッキ(ハードクロムメッキや工業用クロムメッキ)
-
機械部品に多く使用されている処理方法です。JIS規格では、膜厚2μ以上、硬度HV750以上と定められています。電気メッキの中では、最も硬度が高いメッキ処理で、耐摩耗性・耐食性に優れています。寸法精度が必要となる箇所につきましても、メッキ厚を考慮し切削、メッキ処理しております。
アルマイト
-
アルミへの表面処理の代表はアルマイトで、陽極酸化皮膜を作る処理のことです。アルミの表面に人工的に分厚い酸化アルミニウム被膜を作る事によって、アルミの耐食性、耐摩耗性の向上を目的として行われます。その他には、装飾や他の機能の付加を目的として行われることもあります。
アルミは1000~7000番台の材質、アルミ合金などに処理が可能です。ちなみに、1000番台→5000番台→6000番台→2000番台→7000番台の順で、1000番台が一番処理しやすく、7000番台が一番処理しにくいです。
白アルマイト(アルマイト加工処理)
-
白色に着色する処理ではありませんので、色はアルミ素材に近い色となります。膜厚は6~10μ、使用目的は防錆で、寸法精度の要求が高いものに使用しやすいです。
カラーアルマイト
-
様々な色に着色するアルマイト処理です。代表的な色は黒色ですが、ほかにも青・赤・緑等対応可能です。膜厚は15~30μ、使用目的は装飾のためのカラーリングです。目に見える箇所に使用される部品ではよくカラーアルマイトの依頼があります。
艶消し黒色アルマイト
-
アルミの素地の表面をブラスト等の前処理で艶消し状態にし、黒アルマイト処理を行うことで、光が反射しにくい表面にすることが可能です。メッキ後に摺動性を向上させたい場合に選定されます。
硬質アルマイト処理
-
皮膜の硬さ、および耐摩耗性に優れたアルマイト処理です。また、絶縁皮膜を希望される場合は、硬質アルマイト処理になります。膜厚を厚くすることにより、破壊電圧と耐摩耗性が向上します。膜厚は50μm程度が一般的となります。また、皮膜の特性はは通電しない「絶縁皮膜」となります。
硬質アルマイトは膜厚を厚くすることで、硬度を変化させることは出来ませんが、破壊電圧と耐摩耗性は向上します。また、光沢が必要となる場合には、バフ研磨を施すことによって光沢を向上させることも可能です。色は材質や膜厚によって変化します。例えば、A2017に30μ程のせると、緑色のような色になります。